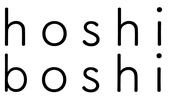トークイベント
星々短編小説コンテスト合評会
第3回星々短編小説コンテスト受賞作について、歴代受賞者が語り合います!
5階 トークイベントスペース
12:00〜13:30 無料
登壇者
糸川乃衣
なごみ
貝塚円花
蓮見
森潤也(ポプラ社)
江口穣(星々事務局長)
司会 羽田繭
内容
歴代星々短編小説コンテスト受賞者の糸川乃衣さん、なごみさん、貝塚円花さん、蓮見さんと、ポプラ社の森潤也さん、星々事務局長の江口穣が登壇!
第3回星々短編小説コンテスト(テーマ・地図)受賞作の合評会です。
受賞作を通して、小説についてじっくり考える90分。
歴代受賞者と星々のスタッフ、そしてプロの編集者が小説創作に寄せる思いを語り合います。
◆合評の対象となる作品
第3回星々短編小説コンテスト(テーマ・地図)
10000字部門正賞
「フロアマップ」桃澤うみ
10000字部門佳作
「砂に刻まれるものたちへ」藤井佯
5000字部門佳作
「しかくを切り取るみかたのこと」長尾たぐい
*作品は選評とともに「星々」vol.5 にも掲載されています。
また、受賞作に対する皆さまの感想やご意見も募集しております。
いただいたご意見はできるかぎり壇上でご紹介させていただきます。
登壇者への質問も歓迎です。
*感想・質問フォームの受付は締め切りました。
登壇者プロフィール
◆糸川乃衣
埼玉県出身。「握りしめるための石ころをさがす」で第1回星々短編小説コンテスト正賞。「叫び」で第3回かぐやSFコンテスト審査員特別賞を受賞。SFレーベルKaguya Booksより短編集『我らは群れ』を刊行。雑誌星々に数々の作品を毎号寄稿。
お話を読んだり書いたりする者のひとりとして、語りの不均衡に抗ってゆきます。
Xアカウント @Itokawa_Noe
◆なごみ
静岡市在住。「長方形の向こう側へ」
「賞状を燃す」、「シアターなないろ」、「交差点で立ち止まる」
星々短編小説コンテストへの応募から小説を書き始めました。「
Xアカウント @753_3
◆貝塚円花
東京都生まれ。北海道在住。
「悪い儀式」で第2回星々短編小説コンテスト一万字部門正賞。
Xアカウント @madokaizuka
◆蓮見
東京都在住。
「老害ラプソディ」
◆森潤也
出版社のポプラ社にて宣伝デジタルマーケティングユニットのマネージャーを勤める。
書籍のプロモーションを行いながら編集者として小説の編集も手掛けており、担当ジャンルは文芸書・時代小説・ライト文芸など。主な編集作品に、ほしおさなえ『活版印刷三日月堂』、凪良ゆう『わたしの美しい庭』など。
Xアカウント @junyamegane
◆江口穣
東京都生まれ。幼少期をアメリカ合衆国コネチカット州、東京都町田市などで過ごしたのち計26度の転居を経験。2020年の星々発足時より事務局長として各種講座などの運営や雑誌「星々」編集に携わる。2024年5月、星々の本棚シリーズより個人作品集「1998年からのラプソディ」を刊行。
Xアカウント @JoEguchi
◆羽田繭(司会)
静岡県出身。現在は神戸市在住。2021年より星々運営スタッフ。2023年5月、星々の本棚シリーズより個人作品集「とおい、ちかい、とおい」を刊行。 いつかイタリアに行きたい。
Xアカウント @tea_for_four
関連企画
◆星々贈賞式
文芸博当日、15:20から5階トークイベントスペースにて、「星々贈賞式」が開催されます。
関連ブース
Map8。受賞者・藤井佯さんのブース。
Map19。登壇者・糸川乃衣さんのブース。
Map7。登壇者・貝塚円花さんのブース。
Map1〜4。星々のブース。
第3回星々短編小説コンテスト(テーマ・地図)受賞作が掲載された雑誌「星々vol.5」のほか、登壇者の作品が掲載された「星々」の既刊が販売されています。
また、雑誌は星々のオンラインショップでもお買い求めいただけます。
この記事をシェア